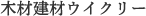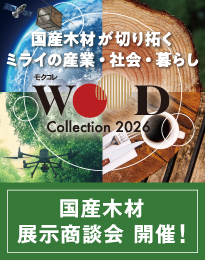CLT、その可能性と課題
設備投資は行政が後押し
CLT(直交集成板)が日本で注目された切掛けは、2010年9月に国土交通省で開かれた第5回「木の家づくりから林業再生を考える委員会」(養老孟司委員長)で中島浩一郎委員(銘建工業)が、「杉クロスラミナの開発」について中間報告を行ったことだろう。その後の森林・林業再生プランや自民党政権に代わってからも成長戦略に盛り込まれるなど、政治の場で林業再生に向けた具体策として取り上げられることが増えた。
CLTはラミナを3層以上積層した集成板で、1980年代にオーストリアで開発が始まり99年からKLHが商業生産を開始した。2000年ごろから急速に市場を拡大し、10年には年間6万㎥に生産が拡大した。このころからKLH、ビンダーホルツなどのメーカーが日本市場の開拓に向けて取り組みを開始したが、新たな木質構造材料として法的な整備が必要なことから、海外のCLTの導入はごく限られたものになっていた。KLHが杉ラミナをオーストリアの工場に送り、テスト生産するなど、国内集成材メーカーなどと日本市場の開拓に向けた取り組みを行った。それが冒頭の国土交通省と林野庁の共管による委員会で取り上げられ、市場拡大に向けた環境整備につながり、14年にはJASが制定された。16年に基準強度の告示、一般的な設計法なども告示化される見通しで、16年がCLT元年になるともいわれている。
そのため現在の需要はCLTを使って地域興こしをしたい地方自治体などが中心で、国土交通省や林野庁の補助事業として公共建築で使われるのが主流だ。
一方、行政主導でCLTの地域協議会を設立し、自治体、林業、製材、集成材などのメーカーを巻き込んでCLT工場やラミナ供給を担っていこうという動きが活発化している。現在、CLTのJAS認定は銘建工業と山佐木材が取得しており、レングスがこれに続く見通し。中東が集成材と併用ラインの導入を決め、福島県でもCLT工場の建設の計画がある。このほかにもCLT製造に向けた動きは活発化していて、需要より先に生産体制の整備が進みそうだ。
工場が各地に建設され、中断面構造用集成材並みの価格で供給できるようになれば市場が広がってくるだろうが、現状では限られた需要のなかでどうやってコストを下げていくのかが問われている。
記事ランキング
- 国内の合板メーカー 値上げで足並みそろう
- かつら木材商店 丸太消費量拡大を計画
- セブンーイレブン・ジャパン 標準型店舗の木造第1号がオープン
- 銘建工業と玄々化学工業 CLTで準不燃材料認定取得
- KAMIYA 国内初、高さ3メートル室内ドア開発
- YKK APランドスケープ 田主丸緑地建設を子会社化
- 日本ノボパン工業 3月21日から各種PB製品、10%値上げ
- 中部電力 4カ所の小規模バイオマス発電事業から撤退
- サイプレス・スナダヤ CLT年間5000㎥を安定受注
- スタッフ 約8億円投じ生産性15%向上

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画