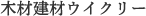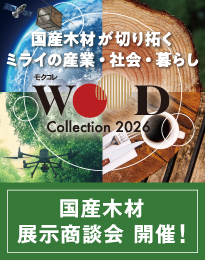都道府県の木造振興策
新築からリフォームまで手厚く
あの手この手で木材需要後押し
都道府県が木造住宅の振興や地域材活用のために補助を行う制度が広がり、2013年には林野庁の木材利用ポイント制度まで広がりを見せた。今回47都道府県を対象にアンケートを実施、地域材を使った木造住宅に対する補助制度がないのは、青森、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、香川、長崎、鹿児島、沖縄の10都府県だけだった。静岡県では15年度は1,100棟の予算を計上、山口県も1,000戸、群馬県は構造材補助で730戸、内装材で60戸など県によっては木造住宅着工数の1割近くが補助を受けているケースもある。また、県によっては戸当たり100万円を超える補助もあり、地方にとって地域材活用の補助制度は重要な位置付けとなっている。
都道府県が地域材を使った木造住宅の振興策を始めたのは02年のことで、この年秋田県が実施した柱材プレゼントが各地に広がるきっかけになった。当初は、地域材を使って木造住宅を建てるときに柱などをプレゼントする制度が導入され、それが戸当たりの補助金や住宅ローンに対する利子補給などとなり、現物支給から補助金へと変わっていった。
それまでの補助制度の多くは供給事業者向けの設備投資などに対するものが主で、住宅の施主、いわば一般消費者を対象にしたものはまれだった。補助事業を通じて一定の需要拡大に寄与することで地域経済を活性化し、地域の産業や雇用にも寄与しようとする流れだ。一部の協同組合などへ設備投資の補助を行うより、需要を喚起できるような補助制度が業界からも歓迎され、各地に広まっていった。
当初、補助制度の対象は新築の木造住宅に限定されていた。その後リフォームや、一部では非住宅木造や内装木質化にも補助を行うケースも出ている。
これらの制度が始まって10年以上が経ち、WTOの内外無差別のルールに都道府県などの補助制度が抵触しないかとの懸念もあった。
林野庁の木材利用ポイント制度は、国が実施する補助制度として対象地域材を国産材に限定できないなかで、独自にルールを設けて、農山漁村の経済や雇用へ寄与することを目的に実施された。当初は国産材の一部のみを対象地域材に指定していたが、次第に門戸を広げざるを得なかった。これは、国が地域材振興に直接的に関与することの難しさを示した形になったともいえそうだ。
記事ランキング
- 国内の合板メーカー 値上げで足並みそろう
- かつら木材商店 丸太消費量拡大を計画
- セブンーイレブン・ジャパン 標準型店舗の木造第1号がオープン
- 銘建工業と玄々化学工業 CLTで準不燃材料認定取得
- KAMIYA 国内初、高さ3メートル室内ドア開発
- YKK APランドスケープ 田主丸緑地建設を子会社化
- 日本ノボパン工業 3月21日から各種PB製品、10%値上げ
- 中部電力 4カ所の小規模バイオマス発電事業から撤退
- サイプレス・スナダヤ CLT年間5000㎥を安定受注
- スタッフ 約8億円投じ生産性15%向上

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画