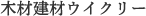次世代の木材技術開発
新たな技術で市場を拓け
木質素材の潜在能力を探る
新たな木材の加工技術や建築構法の開発が盛んになってきた。杉を中心とした国産材の蓄積が増加し、利用技術の確立が大きなテーマになっていることや公共建築物等木材利用促進法の施行で、非住宅の中大規模木質構造建築物に対する需要の増加が見込まれる。これは循環型資源としての木材、CO2固定機能としての木材利用など、木材のを使用が環境に対してプラスになる印象が高まってきたことも後押ししている。
構造材料の分野では、低質材を原料に工業化手法を使って安定した強度、品質の木質材料を開発するのが、最近の大きな流れだった。また、構造用集成材やLVLなど接着等の方法で再成型することで均質で工業的な材料にしていくことが木材加工技術の大きな流れだった。しかし、最近の開発傾向としては木材を大きな断面で接着するなど、使用量を増やす方向に変化してきた。木材が炭素を固定する性質により、大量に使う方法を模索していることや、防・耐火性能の面では、木材そのものが燃え代設計にあるように表面が炭化していくため燃焼を遅らせる機能がある。
海外技術の導入も
大館樹海ドームのような大型木造ブームが去ったあと、日本では住宅レベルの木造建築が需要の大部分を占めるようになり、新たな構法や架構方法の開発はあまり行われなくなっていた。その一方で欧州ではLVB(ラミネーテッド・ベニヤ。ボード)、CLT(クロスラミナティンバー)など面構造の木質材料が急速に普及してきた。ロンドンの木造9階建てマンションはCLTによるもので、プレキャストコンクリートの木材版のようなものが普及し、木造オフィスビルや学校などの建築物で使われている。構造分野では材料認定の壁があり、海外で開発された構造材や構法が国内で使用されるようになるには、今しばらく時間がかかりそうだが、新たな木質構造の流れとして注目される。
記事ランキング
- 【電子版速報】ナイス旧経営陣裁判 平田、日暮両氏、無罪確定 東京港木材製品需給 在庫2ヵ月連続減で12万立方㍍台に
- SINACO 「クリーンカットランニングマシン」を開発
- 主な記事
- 【電子版速報】東京港木材製品需給 在庫2ヵ月連続減で12万立方㍍台に
- 福島で発芽・幼苗専門施設整備 木造建屋で省エネ化、年間通して生産

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画