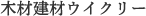ここまで来た木構造建築物
住宅に次ぐ木材利用へ
木造耐火建築も除々に増加
公共建築物等木材利用促進法が2010年10月に施行されてから、約2年半が過ぎた。当初、林野庁では、公共建築物のうち低層のものを木造化することで年間500万㎡の新たな木材建築物の需要をつくり、1㎡当たり0.3㎥の木材を使用することで年間75万㎥、原木換算で150万㎥の需要を創造すると試算していた。これに加えて、低層以外の木造化、民間への波及効果などでさらに大きな需要創造が見込まれている。
木材利用に関する方針策定も4月5日時点で1,742市町村中1,114が策定済みで、方針策定率は64%。県内のすべての市町村で方針を策定しているのは青森、岩手、秋田、栃木、富山、石川、長野、岡山、広島、徳島、高知、佐賀、大分、宮崎、鹿児島の15県。こうした取り組みが木材需要の拡大に寄与していくものとみられる。
民間を含めた非住宅の木造建築物の需要は木材利用促進法施行前の09年の308万3,000㎡から10年は347万2,000㎡、11年は352万7,000㎡、12年は377万2,000㎡と年々増加している。08年度の公共木造建築物は111万㎡と非住宅木造の3分の1程度の規模で、民間の非住宅木造建築物の比率が高いことが分かる。
実際にプレカット工場では受注物件の1割ほどが非住宅物件になっているとの声があり、1物件当たりの規模が大きいことから工場の稼働にも大きな影響を与えるようになってきた。300~500坪くらいの物件でも全体の加工が月間5,000坪規模の工場なら1割に当たり、住宅の加工工程に影響を及ぼす可能性も出てくる。
最近では木造耐火構造の物件が話題になり、大阪木材仲買会館、音の葉カフェ、イオンタウン新船橋など意匠的に木材を現しにした木造耐火建築物が相次いで竣工した。延べ床面積1万㎡を超える木造商業施設「サウスウッド」の工事が始まり、都内では木造5階建て(1階はRC造)共同住宅が6月にも完成するなど、木造耐火構造の分野での話題が多い。2×4工法による木造耐火建築物は累計で2,000棟を超え、木造でも耐火構造とできることが認知されてきた。これまではメンブレン型の木造耐火が主流だったが、竹中工務店の「燃エンウッド」、鹿島建設の「FRウッド」など、意匠的に木材を見せることができ、耐火性能も持つ部材開発が進んでおり、木構造建築物の可能性を広げていくことが期待される。
記事ランキング
- 9月の住宅会社受注 秋需見えず、戸建て受注伸び悩む
- 北関東の国産材丸太 栃木で杉柱取りが1万7000円突破
- 大屋根リング材、能登の復興住宅資材に 石川県珠洲市が無償譲渡
- 全国森林組合連合会 主伐関連事業が伸長
- 柚一 年末にも稼働再開
- タナカ 楽に打てる「かすがい」新商品発売
- トヨタ自動車 レーザー描画で受け口基準線を把握
- 一建設 木製筋違耐力壁「HW5.0Σ」を公開
- 出光興産 ブラックペレット、年300万トン供給へ
- 大林組 中規模建築の純木造設計を支援

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画